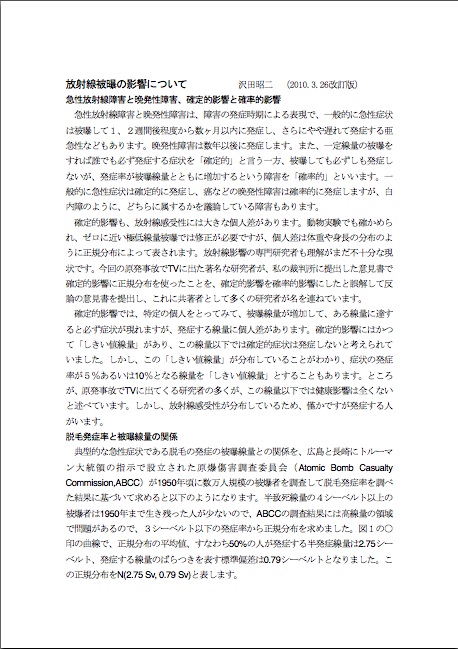日本原水協の沢田昭二代表理事の被曝線量についての解説を紹介します。(2010.3.26改訂版)
****
被曝線量について関心が高まっていますが、この被曝線量ではただちに健康に影響はないという説明があり、それがどの程度か説明を求められることが多くなっていると思います。そこで、以下のような広島原爆被爆者の具体的数値を含めて、被曝影響の説明の資料を提供します。
沢田昭二
****
放射線被曝の影響について
急性放射線障害と晩発性障害、確定的影響と確率的影響
急性放射線障害と晩発性障害は、障害の発症時期による表現で、一般的に急性症状は被曝して1、2週間後程度から数カ月以内に発症し、さらにやや遅れて発症する亜急性などもあります。晩発性障害は数年以後に発症します。また、一定線量の被曝をすれば誰でも必ず発症する症状を「確定的」と言う一方、被曝しても必ずしも発症しないが、発症率が被曝線量とともに増加するという障害を「確率的」といいます。一般的に急性症状は確定的に発症し、癌などの晩発性障害は確率的に発症しますが、白内障のように、どちらに属するかを議論している障害もあります。
確定的影響も、放射線感受性には大きな個人差があります。動物実験でも確かめられ、ゼロに近い極低線量被曝では修正が必要ですが、個人差は体重や身長の分布のように正規分布によって表されます。放射線影響の専門研究者も理解がまだ不十分な現状です。今回の原発事故でTVに出た著名な研究者が、私の裁判所に提出した意見書で確定的影響に正規分布を使ったことを、確定的影響を確率的影響にしたと誤解して反論の意見書を提出し、これに共著者として多くの研究者が名を連ねています。
確定的影響では、特定の個人をとってみて、被曝線量が増加して、ある線量に達すると必ず症状が現れますが、発症する線量に個人差があります。確定的影響にはかつて「しきい値線量」があり、この線量以下では確定的症状は発症しないと考えられていました。しかし、この「しきい値線量」が分布していることがわかり、症状の発症率が5%あるいは10%となる線量を「しきい値線量」とすることもあります。ところが、原発事故でTVに出てくる研究者の多くが、この線量以下では健康影響は全くないと述べています。しかし、放射線感受性が分布しているため、僅かですが発症する人がいます。
脱毛発症率と被曝線量の関係
典型的な急性症状である脱毛の発症の被曝線量との関係を、広島と長崎にトルーマン大統領の指示で設立された原爆傷害調査委員会(Atomic Bomb Casualty Commission,ABCC)が1950年頃に数万人規模の被爆者を調査して脱毛発症率を調べた結果に基づいて求めると以下のようになります。半致死線量の4シーベルト以上の被爆者は1950年まで生き残った人が少ないので、ABCCの調査結果には高線量の領域で問題があるので、3シーベルト以下の発症率から正規分布を求めました。図1の○印の曲線で、正規分布の平均値、すなわち50%の人が発症する半発症線量は2.75シーベルト、発症する線量のばらつきを表す標準偏差は0.79シーベルトとなりました。この正規分布をN(2.75 Sv, 0.79 Sv)と表します。
▲図1
この正規分布では、低線量の1シーベルトで脱毛を発症する人は1.37%、2シーベルトで17.2%、3シーベルトで62.3%、5シーベルトで99.8%の発症と100%発症に近づきます。この正規分布では図2のように、0シーベルトで発症率は厳密に0にならないので、0に近い極低線量では修正を要します。被爆者の調査からも、一般的にも極低線量被曝の影響を引出すことは難しいので、正規分布にもっともらしい修正を行って推定すると、図2のは線のようになり、0.3シーベルト、すなわち、300ミリシーベルトでは0.03%〜0.07%、すなわち1万人が被曝して3人ないし7人の人が発症することになります。しかし、これほどのまれな発症は発見が難しくなると考えられますので、福島原発事故による被曝影響の検出は、白血球減少症のように発症の検出をしやすいもので早期発見に務めるべきだと思います。
▲図2
外部被曝と内部被曝
もう一つの問題は、外部被曝と内部被曝とでは症状発症に至る機序がまったく異なることを無視した説明です。野菜に付着したり、水に含まれた放射性物質を体内に摂取した場合の内部被曝被の影響を、CTやX線を浴びた被曝と比較する説明が行われていますが、体内に摂取した放射性物質が主に影響を与えるベータ線とX線とはまったく異なる影響を与えることを無視した乱暴な説明です。X線やガンマ線は透過力が強く、エネルギーにもよりますが、人体を通り抜けるくらいの透過力です。ところがベータ線は体内では数センチメートルでエネルギーを失ってストップします。この違いは、放射線が伝搬する時に通過物質の分子や原子の電子にエネルギーを与え、その電子が原子や分子から飛び出す「電離作用」を疎らに行うか、蜜に行うかの電離密度の違いによります。
於保源作医師の広島被爆者の急性症状発症率調査では、原爆の初期放射線による外部被曝が主要な影響を与えた近距離では、下痢発症率は、脱毛や紫斑に比べてかなり小さいのに対し、初期放射線が到達しないで放射性降下物による内部被曝が主要な被曝を与える遠距離被爆者の間では脱毛や紫斑の数倍の発症率となっています。この下痢の発症率は、図1に示すように初期放射線による下痢発症率は脱毛に比べて高線量の被曝領域で大きくなる半発症線量の大きい正規分布 N(3.03 Sv, 0.87 Sv) を用い、放射性降下物による被曝の下痢の発症の場合は脱毛に比べて小さい被曝線量から発症率が大きくなる半発症線量の小さい正規分布 N(1.98 Sv, 0.57 Sv) を用いると、脱毛、紫斑、下痢という異なる急性症状の発症率を共通した初期放射線と放射性降下物による被曝線量によって説明できます。このことは外部被曝と内部被曝による下痢の発症の機序の違いによって説明できます。
放射線による下痢の発症は薄い腸壁の損傷によります。外部被曝の場合には透過力の強いガンマ線だけが腸壁に到達できます。しかし、到達したガンマ線は薄い腸壁にまばらな電離作用を行って通過するので、かなりの高線量のガンマ線でなければ腸壁は傷害を受けないので下痢は始まらない。これに対し、放射性物質を飲食で取り込むと、腸壁に放射性微粒子が付着して、主にベータ線によって腸壁に密度の高い電離作用をおこなって腸壁に傷害を与えて下痢を発症させます。このように外部被曝と内部被曝では、下痢だけでなく、発症の機序は一般的に異なるので安易な比較は許されません。
晩発的障害
癌あるいは悪性新生物などの晩発性障害の大部分は確率的影響です。しかし、一般に晩発性障害の原因には、放射線被曝以外にも様々な原因があるので、障害の起因性を急性症状のように放射線被曝であると特定することは困難で、全く放射線被曝をしていない人々の集団の発症率と比較して被ばく影響を求めることになります。特定個人の晩発性障害の放射線起因性を推定しようとすれば、その個人の被曝する前後の健康状態の変化を含め、過去からのさまざまな健康状態や他の疾病の経緯を総合して判定することになります。
被曝線量と晩発性障害の発症との関係を、具体的に広島大学原爆放射線医科学研究所の広島県居住の被爆者の悪性新生物による死亡率を広島県民と比較した論文「昭和43〜47年における広島県内居住被爆者の死因別死亡統計」(広大原医研年報22号;235-255,1981) から、直爆被爆者の悪性新生物による1年間死亡率を用いて求めます。この論文の、直爆1 km以内、1 km〜1.5 km、1.5 km〜2 km、2 km〜6 kmの各区分と被曝していない広島県民の悪性新生物による1年間の死亡率は、図3に示すように、それぞれ 0.504 %、0.454%、0.347%、0.374%、0.186%となっています。これらの死亡率と非被曝の広島県民の死亡率 0.186% との差、すなわち、1年間で悪性新生物による死亡率の増加と、初めに述べたABCCの脱毛発症率から求めた初期放射線と放射性降下物による合計被曝線量の 3.88 Sv、2.24 Sv、1.56 Sv、0.85 Sv、0 Sv が、比例関係にあるとすると、1Sv の放射線被曝によって0.082 %〜0.22 %の増加、間を取って約 0.15 % 増加することがわかります。
▲図3
低線量被曝の部分についての悪性新生物による死亡率の増加と被曝線量との関係も、比例関係が維持されると仮定すると、0.1Svの被曝では0.015 %の死亡増になり、10 mSv = 0.01 Sv の被曝では 0.0015 %の死亡増、すなわち100万人が10 mSv被曝すると悪性新生物によって死亡する人が約15人増えることになります。
以上が典型的な確率的影響の悪性新生物の増加と被曝線量の関係です。晩発性障害に対しても個人差が大きく分布していると考えられますが、こうした分布も含めた結果として、発症率や死亡率の増加が被曝線量に比例することになっています。
以上