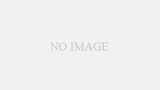北海道高校生・学生ツアー参加者から原水爆禁止2007年世界大会の感想文を紹介します。
文中仮名
僕は中学2年生のときに一度広島の方の世界大会へ参加しました。当時は、原爆とか戦争とか、そういうことは何もわかっていなくて、ただ親に連れられて行っただけだったので、そのときのことはほとんど何も覚えていません。今になって、「どうしてもっと真剣に参加しなかったんだ!」と後悔しています。
あの当時は全く印象に残らなかった世界大会でしたが、今年は違いました。今に至るまでにいろいろなところで原爆や戦争というものについて少しずつ触れてきて、いつのまにか大きな関心事になっていたからです。
1日目は原爆資料館へ行きました。入場券を買って、館内に入るときに、中学生のときの適当に眺めていただけの資料館の記憶が一瞬浮かびました。「今度こそ真剣に見るんだ」、そう思って中に入りました。館内に入り、展示物を順番に見ていると、数分もしないうちに愕然となりました。これほど残酷な展示物を全く覚えていなかったからです。一つひとつ丁寧に見ていくと、だんだんと胸が苦しくなっていくような感じがしました。被爆者の方の証言が書かれている展示の所では、訴えかけてくる途方もない苦しみに泣きそうになってしまいました。展示物を全て見終わったあと、この惨状が今自分が立っている同じ地で起こったのかと考えると、非常に怖くなりました。
3日目の青年のひろばでは、体育館でのシンポジウムの方に参加しました。そこで、原爆症認定集団訴訟についての詳細な話を聞き、あれだけの辛い体験をされた方が、なぜ、今現在も苦しみ続けなければならないのか、そんな理不尽な話があるか、と思いました。3分間程の短い時間で認定、認定却下の判断をしようとする厚労省。症状が人によって違うのは当たり前なことです。それに、被爆者の方の気持ちを考えたなら、そんな短時間で済ませられるはずがありません。国はもっと真摯な態度で被爆者に向き合うべきです。被爆者の声にしっかりと耳を傾けて聴いてほしい。そのあとには、熊本県での原爆症認定訴訟支援活動の話を聞きました。300人の被爆者への聴き取りという、その活動の規模の大きさに驚いたのと同時に、地元でもっともっと頑張らなければ、頑張りたい、と強く思いました。
今回の世界大会では、原爆の本当の恐ろしさをまず最初に知りました。その次に、国の理不尽な対応のために今もなお苦しみ続けている被爆者がいること、まだまだ原爆の被害は続いているということを知りました。
僕は、被爆者の方たちを尊敬しています。あれだけの体験をされても力強く生きて来られた方たちだからです。そして、本来なら国も敬意をもって接していなければいけない方たちだと思います。それなのに、救済しようとしない。間違っていると思います。
中学生のときには全く平和や戦争に関心がなかった自分でも、少しずつ、被爆者の話を聴いたり、戦争について話し合ってみたり、平和のことを考えてみたりしていくことで、ここまで思うことができるようになりました。国も含めて、原爆について、被爆者について全く関心のない人々も、こうした問題に少しずつでも触れていけば、きっと関心を持ってくれるようになるはずです。そう思いながら、これからの活動を進めていきます。
(T.T)
2年前、修学旅行で広島を訪れ、原爆資料館などを見学した時は“原爆って恐ろしい”という思いが強く残ったことを覚えている。今もその思いは変わらないが、今回の世界大会に参加してみて、いろんな人の話を聞き、いろんな場所を見学するほど、悲しくてしょうがなかった。あんなに暑い夏の日、何百度という熱風に吹かれ、吹き飛ばされ、さらには放射能という死の灰を浴び・・・。考える間もなくなった方も、何日も苦しみながらなくなった方もいるだろう。そして今、現在も苦しんでいる人も。そんな人たちのことを考えるたびに涙があふれてきた。こんな理不尽なことがあっていいのだろうか、と。しかしその惨劇が再び繰り返されるのだとしたら。こんなに悲しいことがあるだろうか。
私が分科会のとき、お会いした被爆者の方は言っていた。“私の姉は苦しんで死んでいった。お医者さんに何度も、生きたい、生きたい、と言って。その姉のことを思い出すのは恐ろしくて今まで話してこなかったけど、こうして誰かに話すことで少しは姉のためにもなるのではないかと思った”と。髪が抜け落ち、腐った内臓が口から出てきていた、というお姉さんの姿は私の想像を超えたものだった。お姉さんは23才だった。
今回の大会をきっかけに核廃絶の想いをよりいっそう強めるとともに、反戦への想いもよりいっそう強まった。核というのは絶対この世に必要の無いものだと思うが、核だけがなくなれば良いわけではない。その大元である戦争、これがなくなってこそ真の平和が訪れるはずだ。だからまず私にできることは今回学んだ事実を少しでも多くの人に広めることだ。私もそうだが、私たちはあまりにも何も知らなさ過ぎると痛感した。原爆について、戦争について、そして実際日本で起こったことについて。戦争を再び繰り返させないためには、戦争を知らない世代の私たちが学んでいかなくてはいけない。事実を知らないことには正しい判断はできない。嘘の情報に惑わされないためには賢くならなくてはいけないのだ。今回私はとても貴重な体験をさせてもらったのだから、それを一人でも多くの人に伝え、知ってもらう必要があると思う。でも正直言うと、友達にこういう話をするのはなかなか勇気がいることだけど、行動しなきゃ始まらないから。やるぞ!
(Y.K)
私が原水禁世界大会に参加するのは今年で二回目ですが、前回とは大きく違うことがあります。それは、今回は私がこのツアーの代表として参加することです。それは、私にとってとてもとても大きなプレッシャーでした。
八月六日の出発の日、千歳空港のテレビで、広島の平和祈念式典の様子を見ました。子供代表が読み上げた、「平和への誓い」。「途切れそうな命を必死でつないできた祖父母たち」というフレーズに、この一年間にお会いした被爆者の人たちを思い出しました。想いを内に秘めて、切々と語ってくれた被爆者。涙を流し、肩を震わせながら、それでもなんとか伝えようとしてくれた被爆者。東京の座り込み行動で見た、文字通り体を張って訴えていた被爆者。ビキニデーでは、被爆者こそが原水禁運動の原点であることを、強く感じました。二度の原爆投下から、ビキニ被爆を経て、現在まで…。差別と偏見、忍び寄る病気の恐怖におびえながらも、まさに、「途切れそうな命を必死でつないできた」被爆者の方々。私はその迫力のある姿を片時も忘れることはできません。そして私たちをも巻き込んだその運動は、今年も広島・長崎に多くの人を集めています。
私たちは長崎に着いて、まず初めに平和資料館へ行きました。長崎の資料館では、外国人被爆者についての展示が印象的でした。外国人被爆者の証言が映像で見ることができたので、私は日本軍の捕虜になったオーストラリア人の被爆者の証言を見ました。その人は、日本軍からひどい差別、暴力を受け、原爆投下によって、その支配から逃れることができた、と語っていました。これは、多くの韓国・朝鮮の人たちの意見と同じです。刑務所に入れられ、毎日毎日暴力を受け続けてきた人から見れば、原爆投下が戦争を終わらせたように見えたかもしれません。しかし、その当時の日本には、すでに戦争を継続する余力が無かったことは明白です。原爆投下が第二次世界大戦の終結と無関係だということは、これからもしっかりと訴えていかなければならない、と思いました。
長崎は北海道とは正反対で、山や丘陵地が多く、狭い坂道があちこちにある、ごちゃごちゃとした町並みです。凹凸のあるその地形を見回したとき、なぜか、原爆がこの街に落ちる映像が、まるでコンピュータグラフィックのように頭に浮かんできました。山の上のホテルから、盆地を見渡したときにも同じことが起こりました。原爆が落ち、その爆風、熱線、そして放射線が、山の斜面に沿って、すべてを破壊していく。そんな、まるでアニメーションのような映像が頭に流れ、しかしはっと気づくと、そこには夜景のきれいな美しい街がありました。私は長崎の街中で、何度も何度もその変な感覚にとらわれました。
今回は原爆症認定訴訟の分科会に参加したこともあり、世界大会全体を通して私が一番感じたテーマは、原爆症認定訴訟でした。閉会総会で、東京の原告がまた一人亡くなったことを聞きました。東京地裁では三月二十二日に原告勝訴の判決が出て、三十日に国が控訴しました。もしもあの時、国が控訴をしなければ…、と思うと、とても怒りがこみ上げてきます。また、八月九日には、長崎の原告が亡くなりました。長崎地裁では七月三十一日に結審したばかりでした。
国の対応が遅いばかりに、無念のうちに亡くなっていく多くの被爆者たち。どんなに願っても、過去を変えることも、根本的に被爆者の苦しみを取り除いてあげることも、そしてそれを軽減してあげることさえできない、現在の私たち。それは、その責任のある国にとっても同じことです。国にできることは、せいぜいその過ちを認め、謝罪すること、経済的に被爆者を援助することだけです。しかし、そんなささやかなことでさえ、国は行おうとしていません。
世界大会に参加し、被爆者に残された時間が本当に少ないことを改めて実感しました。私は札幌に帰ってきて、被爆者の聞き取り、訴訟の支援をしていこうと思っています。私は被爆者のために活動したいと思っています。しかし、被爆者の方々は、自分のためというよりはむしろ、私たちのためにたたかっています。もうこれ以上、被爆者を増やさないでほしい、核兵器のない平和な世界を作りたい、それが彼らの願いです。原水禁運動の原点となったビキニ被爆で亡くなった、久保山愛吉さんの言葉、「原爆の被害者は私を最後にしてほしい」という想いは、50年以上たった今でも、おおくの被爆者、支援者に受け継がれ、今なお原水禁運動の原点であり続けています。そして私はこの想いを被爆者の方たちから「継承」し、より多くの人に「発信」していきたいです。
(C.F)
私は、今回、原水爆禁止世界大会に初めて参加して多くのものを得ることができました。一つは、月並みかもしれませんが、これだけ多くの人がこの運動に関わっていることがわかったことです。自分たちの地域や学校で活動していると、周りには多くの無関心な人たちがいて、自分たちが活動したぐらいで何が変わるんだろうと無力感にとらわれることもあります。しかし、熱気に包まれた世界大会の会場で様々な人の話を聞き、最終的に50万羽を超えた「21万羽折づるプロジェクト」の折り鶴を見てこんなに多くの仲間や支えてくれる人たちがいることにとても勇気付けられました。
二つ目は、これも当たり前のことですが、夏のナガサキを体験できたことです。今まで被爆の体験を本で読んでもわからなかったことが、長崎に来たことでリアルに感じることができました。その一番の理由は暑さだと思います。4泊5日の間ずっと天気もよく気温も湿度も高かったので日陰にいても夜になってもとにかく暑くて、日中歩いて移動すると空のペットボトルがかばんの中に2つ、3つと増えていくような暑さでした。こんな暑さの中、全身火傷で地面に寝かされていたけが人はどんなに水が飲みたかっただろうか、焼け野原の何万もの死体が放つ言葉で表せないようなにおいとはどんなものだったのか、私たちには想像するしかありませんが北海道で想像できることと長崎に来て想像できることには大きな違いがありました。
三つ目は、これから活動していくときの課題がいくつか見えてきたことです。大会2日目の分科会で市内の被爆者の方を訪問してその話を聞いたあと、一緒に訪問した青年たちとグループトークをしました。その中で何人かの人が「生の声を聞けてよかった。」と言っていました。これには私も同感です。しかし、被爆者の方はみんな高齢で健康に不安を抱えています。被爆の話を直に聞けなくなるのもそう遠いことではないはずです。そうなったとき今回の青年のひろばのテーマでもある「継承と発信」をどう実践していくのかは、私たちの世代の大きな課題だと思います。また、ある人が、この世界大会に参加するまでこういう活動には近づきづらかったと言っていたのがとても印象に残っています。平和運動といってもいろいろありますが、核兵器反対の活動は比較的賛同が得られやすいものだと思います。実際、大学のメーリングリストを使って今長崎にいることを同じ専攻の人全員にメールで送ったらいくつか返信が来て中には原爆反対がんばってよって返してくれる人もいてちょっと驚きました。しかし、問題なのはこういう好意的な人を運動に巻き込むことができないでいることです。このことが、活動をやっている人自分たちと違うよくわからない人、あるいは何か自分たちにまねできないすごいことやっている人などの壁を作られてしまう原因のひとつだと思います。自分たちで継承するだけでなく周囲へ発信していくことも私たちの大きな課題です。
最年少初参加なのにずいぶん大きなことを書いてしまいました。学習も実践もまだまだできてない自分への励ましの意味もあるんですが実際どこまでできるかはわかりません。これからも自分にできることを自分なりにがんばっていきたいと思います。
(K.O)
原水禁世界大会には、去年に引き続き2回目の参加となり、今年は北海道代表団の事務局と学生ツアーの引率(中途半端になってしまいましたが…)を兼ねての参加となりました。
今回の大会では、特に北海道や全国の若者と交流するなかで、日常のなかではなかなか考える余裕がないのですが、平和な日本、世界をつくるにはどうしたらよいかを本気で考えることができたと思います。
2日目の分科会で、青年のひろばのパネルディスカッションに参加しました。班ごとに分かれていて、全国の若者と交流する機会があったのですが、熊本大学の学生さんから、「大学の教授と話しをしていたら、原爆投下されたのは被爆者にも責任があるでしょ。」と言われたという話しが出ていました。これはちょっとビックリしました。戦前は天皇が絶対のもとで、国の戦争政策に反対して戦争反対を言っただけでもまわりから非国民扱いされ、そういう活動をすると治安維持法のもとで死刑までありえる状況であり、国家のやることに反対する運動や言論までが法の下で強制的に封殺されていたもとで、被爆者を含む国民が、戦争に反対できず結果として加担したとしても、それを被爆者に責任を問うのはおかしな話じゃないか?と思いました。思ったので言いました。現代に振りまかれている自己責任論が蔓延しているのかなとも思い悲しくなりましたが、事実をその背景も踏まえてしっかり見ていく、伝えていくことが本当に必要なのだとも感じました。
海外代表を招いた北海道青年交流会に参加した看護学生さんと話す機会が3日目にありました。交流会のなかで、平和運動の意義のところでモヤっとしてしまったようでした。話しをした時の最初の質問が新聞やテレビを見てても何が正しいのか分からないということでした。また、平和だけ訴えたとしても平和な世の中を作れる気がしないとも言っていました。とても深くものごとを考えているのだなと思い感動しました。何が正しいのかを判断するには、なるべく多くの客観的な材料や事実に基づいて科学的にものごとを見ていく必要があることや、核兵器を廃絶することや戦争をなくすことだけが平和に繋がるわけではなく、医療の分野で患者さんの権利を拡大していくこと=人権を発展させることも平和に繋がっていくこと、どんな分野でも国民や若者の権利が拡がり、人間がより豊かな生活を送れるようになることも平和に大きく繋がっていくのだということを交流しました。若者は無関心じゃないということを再認識できてうれしかったです。この北海道で、若者が平和について語り合える場をたくさん作って行きたいと強く思いました。参加させていただき、ありがとうございました。
(T.A)
長崎に着いてまず初めに訪れた原爆資料館の被害の展示は、以前広島の原爆資料館を見たときのように、改めて一発の原爆の破壊力すごさと、放射能によっていつまでも被爆者が死の影に脅かされなければならないという非人間性を改めて感じました。
私が一番強く感じたのは永井隆博士の話で自分も被爆して体が苦しい中、被爆者のために身を粉にした働いた姿は医者としてというよりも、人としてすごいと思ったし、小さい子供を残して死ぬことを悔やみながらも、世界の平和をいのり続けていたというのはすごいことだと思いました。
開会総会や世界青年のつどいでは、海外代表の話などを聞いて、国内だけではなく、世界のみんなと団結して頑張ることが核兵器を廃絶することができるのだと思いました。何よりも、日本に侵略されて苦しめられた中国の青年が日本に来て、日本の印象が変わったといって、平和のために一緒にがんばろうというのに感動しました。また、韓国では原爆は日本による植民地支配からの脱却の証としてプラスのイメージがあると聞いていたけれども、世界大会に多くの韓国の青年が参加していたのが印象的だった。
分科会の青年のひろばでは二人の長崎の被爆者の話を聞くことができました。一人の方は、水を欲しがった人に水をあげずに、その人がそのまま亡くなってしまったことを今でも後悔していると話されているのを聞いて、以前広島の被爆者も似たことを話されていたのを思い出しました。被爆者の経験はどれも全く違うものでありながら、同時に同じような経験をして未だに苦しめられている点では同じだということを知り、改めて原爆の恐ろしさを感じました。また、原爆の後遺症で働くのが難しくてずっと差別されてきたことも知り、原爆は様々な面からいつまでも被爆者を苦しめ続けるものなのだと思いました。しかし、一番心に残ったのは原爆を落としたアメリカについてどう思いますか、と尋ねたときにアメリカが憎いんじゃない、原爆や戦争が憎いんだと何度も何度も繰り返して言われていたことでした。核兵器だけではなく戦争をなくしたいという思いを強く感じました。
もう一人の被爆者は、原爆の恐ろしさは知ってほしいが、それだけではなく日本のやった加害についてもしっかり学んで欲しいと言われていました。日本の起こした戦争と原爆というのはつながっているものだから、戦争について多くのことを学ぶことが原爆についても理解を深めることにつながることが分かり、活動と同時に学習することの大切さを知りました。世界大会に行って多くの仲間が全国にいることを知り、一人一人の力は小さくとも、一人一人が学び行動していけば、必ず大きな運動を作ることが出来るんだという思いを持つことが出来ました。
(K.Y)
8月6日から4泊5日で参加した原水爆禁止2007年世界大会(長崎)では時間があるとも思えましたが予定が詰まっていましたので実際には時間が短く感じる中。
昭和20(1945)年8月9日 11時2分に2発目の原子爆弾(ファットマン)が与えた被害の実態を知る事ができ「原子爆弾や水素爆弾を含む兵器と人類との共存は絶対に不可能であり必ず廃絶させ、平和で公正な世界にしなければならない」と『長崎 原爆資料館』や原爆の様々な被害で苦しみながらも勇気を出して語ってくれた被爆者の方々そして、街の中に残っている建物からも私に数々の平和に対する想いを教え、与えてくれました。
そして、本当にあっという間に原水爆禁止世界大会が幕を閉じましたが、これからが核廃絶と平和への活動の始まりだと感じています
ご同行してくださった皆様や陰で支え応援してくださいました皆様に、この場を借りて深く感謝申し上げます。心に残る貴重な体験や経験をさせていただき、本当にありがとうございました。
(T)
私が今回、この学生ツアーに参加しようと思ったのは、本当に些細なきっかけでした。原爆に特別な興味があったわけではなく平和活動をやってみたい、という軽い気持ちで参加しました。だから世界大会という場が、こんなにも多くのことを学べる場だとは思ってもいませんでした。
一日目、私たちは長崎原爆資料館を訪れました。原爆の悲惨さを本や教科書で知ってはいましたが、あまりのむごさに直視できないものも多くありました。一番印象に残っているのは、丸焦げになった少年の写真。顔は墨となりその表情はわからずとも、異様に折れ曲がった左手首が喉もとに当てられ、全身は伸びきり、その様子からこの少年がいかに苦しんで死んだのか、想像を絶するものであることが簡単に予測できました。被爆者の訴えというブースでは身の毛のよだつ体験がたくさん、展示されていました。原爆の正当性を論ずる人々は、これを見てなお同じ事が言えるでしょうか。地獄のような惨状を眼の目に、「しかたなかった」といえるのでしょうか。原爆のむごさを初めてきちんと知った一日となりました。
二日目からはいよいよ原水爆禁止世界大会が始まりました。海外代表も多く、政治的な立場から見た原爆について知ることができ、視野が広がりました。例えば多くの海外代表は、核兵器を廃絶しない限り必ず核は拡散するだろうと述べました。核兵器はどうしても政治的優位に立つための有効な手段として見られてしまいます。核非保有国と保有国に歴然な差が出てしまえば、各国が競って核を作り続けます。それはまるで国境に爆弾を埋め込むかのように、自国までも傷つける危うい一時的な平和を守るに過ぎないのに。また他国から見た日本についても知ることができました。韓国では、日本が核を保有し韓国を脅かすのではないかという不安を抱いている人が9割もいるのだそうです。私はそれを聞いてとても驚きました。唯一の被爆国である日本がそんなことをするわけが無い。そんなばかげたことを心配されるような国に見えるんだな、と。しかし大会が終わる頃にはこの不安が当たらずも遠からずであることが判明し、ショックを受けました。
三日目、分科会の一環として、私たち学生ツアーのメンバーは「青年の広場」に参加しました。町の公民館に出かけていって、被爆者のお話を実際に聞いたり、それを基にグループトークをしたりするという企画です。そのグループトークの最中に、日本がすでに戦争へ足を向けていることを知ったのです。原爆症認定をなぜ国が渋るのか?北朝鮮の脅威を、なぜ国がそれほどまでに主張するのか?その答えは、「戦争をするために」という一点にたどり着いてしまうのです。原爆症を認定すれば、それにより「戦争の被害が拡大」してしまう。惨事を更なる惨事として国民が認識すれば、より国民の武装に対する賛成を得られなくなってしまう。そして北朝鮮に対する国民への恐怖をあおることで、武装の必要性を訴えかける。もはや戦争への外堀が埋められつつあることを知って、私は愕然としました。
被爆した国は、日本だけです。日本人が原爆の恐ろしさを訴えていかなくて、どうしてこの悲惨さが伝わるでしょうか。被爆者たちの平均年齢が70を超え、語りべが減っていっている今が、本当に動かなければならないときだと思います。日本を戦争する国に変えないため、これ以上被爆者を出さないため、私たち若者が動き出していかなければ、と心から思うことができました。今回私に行く機会を与えてくださった多数の方々に心から感謝します。ありがとうございました。
(M.S)
去年の広島に続いて、今年は二度目の原水禁大会への参加になりました。長崎は坂が多く、歩いて移動するのは一苦労でした。中心街はにぎやかで、広島と同じように路面電車が走っていました。少しわき道に入るとオランダ坂がひっそりと通じていて、趣のある街でした。
原爆資料館は中心街から少し離れた坂の上にありました。地上1階地下2階の建物で、爆心地の様子をうつした写真や爆風でゆがんだ鉄骨、熱さで溶けた小銭などが展示してあり、当時の状況を伝えていました。
いちばん印象深かったのが、入り口に置いてある、原爆の熱で溶けた瓶でした。瓶の説明には、原爆の恐ろしさを忘れないために机の上に置いていたものを、多くの人に原爆の恐ろしさを伝えたいということで寄贈していただいた、ということが書かれていました。それまでも原爆資料館が原爆の恐ろしさを伝え、核兵器を廃絶させたいという考えから建てられたのだろうと感じてはいましたが、そのことをはっきりと認識させられました。
長崎に行くと決まってから、如己堂に行きたいと強く思っていました。長崎には小学生のときに修学旅行で行ったことがあったのですが、他の事はあまり覚えていなくても、如己堂だけはなぜか頭にはっきりと残っていて、もう一度観てみたい、と思っていました。
如己堂は、原爆投下後、自身も重い傷を負いながら負傷者の救護や原爆障害の研究に取り組んだ永井隆博士が、生前に暮らしていた二畳ほどの小屋のような小さな家です。「如己堂」という名前は「なんじの近きものをおのれの如く愛せよ」という意味だそうです。永井博士はそこで、白血病とたたかいながら執筆活動を行なっていたそうです。
小学生のときには、すごく小さい家だなぁ、こんな所で闘病生活していたなんてすごいなぁ、と子どもながらに感心していましたが、今回もう一度見てみて、以前と同じ気持ちになるとともに、永井博士のしせいに感動し、自分も「真理探究の道」を追求するとともに、一刻も早く核兵器がなくなるように何かしないと、と気持ちを新たにしました。
今回のツアーでは、いろんなひととの出会いもあり、苦手なことにも挑戦して、少し成長したようにも思います。これからもこのツアーが続くとともにもっと大きくしたいと思いました。
(M.K)